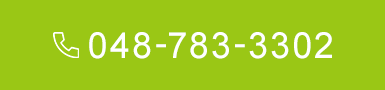第15回です。なんだか不穏なタイトルになってしまいましたが、中身は至って普通です。精神科医であれば、必ずよく遭遇する、患者様の言うことを信用しない場合について書いていこうと思います。
認知症の患者の場合
これがクリニックでは一番遭遇する例です。認知症の方、特にアルツハイマー型認知症の方は、5分前のことすら覚えていないぐらい物忘れが進んでいるのに「いえ、ちょっと、忘れっぽくはあるんですがね、年のせいですよ。なにも生活には困っていません」とおっしゃることがあります。年を聞いても、「いやあ、もう年寄りですからねえ。」とはぐらかしたり、今日の日付を聞いても、「ええ、最近段々寒くなってきましたよね」とはぐらかしたりすることがあります。また、付き添っている家族の方を向いて、正解を聞こうとしようとしたりします。このような行動を「取り繕い」と言います。よく見られる行動です。患者が「困っていない」「日常生活も問題なく送れてます」と話しているときに、後ろから、付き添いの家族が、渋い顔をして、首を横に振ったり手を振ったりと、医師にジェスチャーで伝えてくることもよくあります。なので、医師としては、「本人が困ってないとおっしゃるんだから、いいじゃないですか。問題なくてよかったですね。今日はお帰り下さい」とはなりません。認知症の診断を下し、家族にサービス導入を勧めたり、認知症の薬を処方したりすることになります。
双極性障害(躁うつ病)の躁状態の場合
躁状態と言って、うつ状態の逆、つまり、ハイテンションになることがあります。患者様本人の普段の性格から見て、あきらかにおしゃべりすぎたり、自分が偉くなったような気がしたり、お金を使いすぎたり、極端に活動的になって不眠で行動していたり、といった場合に躁状態を疑うことが多いです。そのような時、本人は「テンション?!高くないっすよ!これが本来の自分なんです!なんで私を病気扱いするんですか?このやぶ医者!だいたい先生は何大学を出ているんですか?!(以下略)」などと言い放ち、テンションが高い自分の状態に自分で気づけない場合がよくあります。まあ、ここまで躁状態が強いときはだいたい入院適応になってしまいます。このようなときは、周りの人から普段の本人の様子を聞き出し、診断を下すことになります。上記のように、医師に食ってかかる人もいて、ここまで分かりやすければ、診断に苦労は全くないんですが、軽度な躁状態の場合、実際にはなかなか難しい判断です。むしろ、重度の躁状態で、精神科病院に入院を要する場合、内心、精神病院で働く中堅からベテランの精神科医は「分かりやすい症例でよかった。そういえば若手の○○先生、精神保健指定医(注:参照)の双極性障害の症例レポートに困っていたな、一緒に入院中の主治医をしてあげようかな」と考えていることすらあります。
注:精神保健指定医:簡単に言うと、精神科の患者を精神保健福祉法に基づき、強制入院をさせる権限などを持つ精神科医です。私も持ってます。精神科専門医とは別物です。医師になり初期研修を2年して、その後、精神科の後期研修に進み、さらに3年してから、取得することができます。その際に、複数の精神疾患の症例レポートの提出が義務付けられており、かなりレポートの審査が細かく厳しいと言われています。私が若手の頃に聞いた噂によると、誤字脱字が複数あったら、それだけで他の記載内容が問題なくても不合格になるんだとか。若手の精神科医は、「レポートを書きやすい、つまり、症状の分かりやすい、典型的な症例の主治医になりたい」と思うものです。私も若手の時はそうでした。もちろん、精神科医としての自分の臨床経験にもなりますしね。5年に一度、指定医更新のために丸1日講習会に出席する必要があります。
今回は以上になります。本当は、入院を要する統合失調症の患者のことも書きたかったのですが、クリニックを開業してから、そういうシチュエーションに接することがめっきり減ってしまいましたので、また、機会があれば書いてみたいと思います。