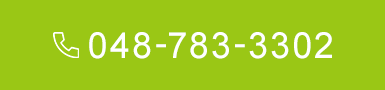今回は詐病についてです。詐病という言葉を聞いたことがあるでしょうか?簡単に言うと、「何らかの利益目的で、わざと嘘の症状を訴えること」です。例えば、交通事故後、腰痛を発症し、本当はとっくに治っているのに、痛みを訴え続けて、会社を休んだり、保険金をもらったり、といったことを指します。要は、悪意のある嘘つきですね。しかし、精神科は不思議なもので、この詐病と似て非なる病気がたくさん知られています。それをいくつか紹介していきましょう。
身体症状症
体のある症状、例えば、頭痛、腹痛、動悸、などを訴え、それが内科、外科、耳鼻科などに行って、検査しても何も異常が見つからず、その結果、不安でたまらなくなる場合、このような病名になります。昔の呼び名だと、身体表現性障害とか、痛みを強く訴える場合には疼痛性障害と呼ばれていました。不安からきている症状ですので、抗不安薬や抗うつ薬を処方することが多いです。または、不安やストレスの原因がはっきりしているなら、そこから離れるように助言する場合もあります。ただ、本当に診断困難な珍しい内科や外科の疾患である可能性は否定できないので、まずはちゃんと検査を受けるべきです。精神科に受診するのは、体の病気が否定されたうえで、というのが条件になります。また、患者本人は苦しんでおり、患者様の主観的には本当に症状があり、嘘をつく意図がない、という点が重要です。
機能性神経学的症状症(変換症)
歩けない、手が動かない、皮膚がしびれる、しゃべれない、痙攣する、などの症状が見られ、それが医学的に説明のつかない症状であるときにつく病名です。脳外科や内科で、「こんな症状は普通は出ないはず」と思われてしまう状態です。ただ、当の本人は、病気により仕事や面倒な人づきあいなどのストレスが免除され、無意識のうちに症状を受け入れており、あまり症状に対して、関心がないときもあります。これを疾病利得と言います。症状があるほうが心理的に得をしている状態ですね。繰り返しますが、わざとやっているわけではありません。治療としては、ストレスの原因があるような場合は、そこから離れるなどのアドバイスをすることもあります。私はてんかん専門医なので、この病気の一部である心因性非てんかん性発作をたくさん経験します。本当のてんかんでないのに、痙攣してしまうんですね。その場合には、周りの人に「本人が痙攣しても毎回騒がないように。また、痙攣してるや、ぐらいの気持ちでどっしり構えて、しばらく安全な場所でほっておくように」と助言することが多いです。周りが「大丈夫?!」と騒ぐほど、本人が無意識のうちに症状を出してしまうからです。ただ、難しいことに、本物のてんかん患者が、心因性非てんかん性発作を合併していることもあり、こうなると、精神科専門医とてんかん専門医の両方を持っている私でも、どれが真の発作かどれが心因性の発作かを即座にはっきりと見分けることは難しいです。診察を重ねて、経過観察していくと、何となく分かってくることも多いのですが・・・。
作為症
これはわざと嘘をつき、周りの関心を引こうとする病気です。詐病とどこが違うのかというと、詐病が金銭や休暇を得たいという動機なのに対して、作為症はまわりの関心を引きたいという動機である点です。昔の呼び方で、ミュンヒハウゼン症候群です。私を含めて中年以降の人は、どこかで聞いたことがあるのではないでしょうか?私は小さいころ、テレビ番組(たしか、世界まるみえ!テレビ特捜部、だったかな)で、代理ミュンヒハウゼン症候群をみて、びっくりした覚えがあります。ミュンヒハウゼン症候群は、本人がお腹が痛い、けがをした、と言うのですが、代理ミュンヒハウゼン症候群の方は、他人、多くの場合は、親が子供に病気を作り出し、その世話をすることで、「熱心な親だ!」と注目されたい場合を言います。子供の点滴に異物を混入させたり、わざと骨折させたりする症例があるようです。
色々書きましたが、実際には、詐病や作為症、つまり、「嘘と分かっててやっている」症例は私の経験上はかなり少ないです。精神科に来られる方は、不安や無意識から症状が出る、身体症状症や変換症のほうが圧倒的に多いです。もちろん、基本的には私は患者様の言うことを信用して治療していくことになりますので、ご安心ください。次回は、例外的に信用しない場合を書いてみようと思います。