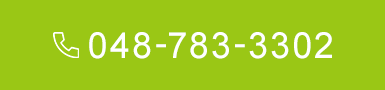うつ病の症例
ここでは、いくつかのうつ病のパターンを紹介していきます。
これまでに院長が実際に経験した症例を紹介していきます。個人情報に配慮して、個人が特定できないようにところどころ脚色しています。
1.仕事の出世を機にうつ病になった男性
来院時
40歳男性です。大手企業に勤めて15年を超えています。半年前に出世し、部下の数も倍増し、仕事上での責任も増えてきました。これまでは、自分のことを考えて仕事をバリバリしておけばよかったのですが、部署全体を監督する仕事も増えて、心身ともに疲弊してきました。3か月前に部下に大きなミスがあり、それを上司から「お前の責任だ」と言われ、そのころから、気持ちが起きこみ、仕事をしていても、集中できなくなってきました。今まではあり得ないようなうっかりミスをするようになり、妻からも「顔色が悪い」と心配されるようになりました。心配した上司から来院を促され、当院に受診しました。
来院後
落ち込みが強く、「自分がしっかりしていないから、会社に迷惑をかけてしまった」と自責的になっていました。医師と話し合い、休職し、抗うつ薬を投与しました。2か月ほどで少しずつ症状が改善し、徐々に外出もできるようになり、趣味だったジョギングもできるようになってきました。休職後、4か月で復職し、今では同じ部署で、ちゃんと仕事ができています。
コメント:
出世を機に、責任が増え、うつ病になるのは、非常によくあるパターンです。個人として仕事ができても、出世してから、周りをまとめていくのが苦手な方もおられます。名選手が必ずしも名監督になれないのと同じですね。その人その人の得意分野、苦手分野があって当然です。
2.職場で退職者が出て、負担が増えうつ病になった女性
来院時
30代女性。事務職を長年務めていましたが、3か月前に同じ部署の同僚が妊娠して、つわりがひどくなり、職場に来れなくなってしまいました。そのまま、その方は退職してしまい、結果として、その方の仕事がそのまま本人にシフトしてきました。上司に相談しても、「今は会社も人が足りないんだ」の一点張りで、仕事量は増える一方。残業時間も増えてきました。2か月前から、徐々に職場に行くと、動悸を感じるようになり、胸やけもするようになりました。頭が回らなくなり、夜の寝つきが悪くなってきました。布団に入ってから、「明日も仕事か」と考え過ぎて、眠れなくなるのです。そのうち、食欲もなくなり、体重も減ってきて、自らの意志で当院を受診しました。
来院後
まずは、睡眠薬のみ処方し、上司に、負担が大きいことを再度伝えるように助言しました。しかし、職場の状況は変わらず、通院開始後もどんどん症状が進み、結局、受診してから1か月後に休職することになりました。休職して自宅療養すると、症状は徐々に改善。3か月後に復職し、その間にその部署にも人員補充がされ、復職後はそこまで忙しくなくなり、順調に業務がこなせるようになりました。
コメント:
職場で、急な退職者、またはうつ病での休職者が出てしまい、ある特定の人に仕事のしわ寄せがいってしまい、結局、その人までうつ病になってしまう、というケースを多く経験します。会社によって、すぐに人員補充をしてくれる会社もあるのですが、ギリギリの人数で回している会社がたくさんあるのも事実。なかなか難しい問題ですね。
3.部署異動後、職場でパワハラに遭いうつ病になった男性
来院時
30代の男性。食品関係の営業部で働いています。1年前に、部署異動になり、今の部署になりました。50代の上司が、口が悪く、営業成績が悪いと部署のみんなの前で「お前はダメだ」「もっと結果を出せ」と強い口調で言われることが続いていました。何とか頑張って仕事をしていたのですが、4か月ほど前から、気持ちが落ち込みはじめ、食欲も低下してきました。夢の中でも、上司に怒られるようになり、仕事のない土日になると調子が良くなるのですが、日曜日の夜になると、仕事が嫌で、家で涙が出るようになりました。どうやら、その問題の上司は、以前もパワハラで、部下を休職に追い込んだ前歴のある人のようです。妻からも明らかに元気がないことを心配されるようになり、当院を受診しました。
来院後
休職として、抗うつ薬を投与しました。徐々に調子は良くなり、外出もできるようになりました。休職してから半年後に、産業医、人事部を含め、職場での面談があり、今までの経緯を伝えました。会社側も、事情をくんで、問題の上司とは違う部署に復職ということになりました。復職後は、問題なく勤務できています。
コメント:
これだけコンプライアンス、ハラスメントが叫ばれる世の中になってきても、平然とパワハラ、セクハラをする人が少数ですが、まだまだいます。これからもゼロにはならないでしょう。いわゆるクラッシャー上司と言っていいのかもしれません。上司の上司に相談するように促しますが、その問題の上司が仕事ができる人だったりすると、なかなか会社も無下にできないという側面があるようです。なお、今回、分かりやすくするためにパワハラ、と書きましたが、本来、パワハラをパワハラと認定するのは、会社や裁判所であり、医師ではないので、誤解の無いようにお願いします。
4.仕事の責任を強く感じ、うつ病になった男性
来院時
20代前半の男性。大学の文学部を卒業し、IT系の会社に就職。SEの仕事を始めました。仕事も2年目になり、責任も増え、徐々に上司の手が離れ、一人で営業先に行かなければならなくなりました。また、新人も入ってきて、その指導も任されるようになったころから、徐々に不安が強くなってきました。3か月前から気持ちが落ち込むようになり、営業先に行くのも恐怖感に襲われるようになってきました。1か月前から、休日も家でぐったりして活気がなくなってきたので、心配した母親から勧められ、当院を受診しました。
来院後
本人と話し合い、休職としました。抗不安薬で様子をみたところ、1か月で調子は改善。会社側も本人への仕事のさせ方も配慮してくれるとのことでした。その後、復職し、仕事は何とか続けられています。
コメント:
若い人の方の一部で、仕事の責任を負うことを極端に苦手に思う方がいます。時代の流れもあるのかもしれません。大部分の方は、復職して、仕事や部下の育成に慣れていくのですが、中には退職して、職を転々とする方もいます。これから以前よりも転職が当たり前の時代になっていくのかもしれません。
5.職場の人間関係でうつ病になった女性
来院時
20代女性です。保育士として働いています。1年前に職場で主任が変わってから、園長と主任の折り合いが悪く、職場が自然と主任派と園長派に分かれてしまったようです。本人は流れで、主任派になったようですが、園長からきつく当たられることが増え、気分が滅入ってきました。3か月前には、些細なミスで園長から呼び出され、30分も説教されてしまいました。そこから、仕事中もトイレで泣いてしまったり、職場に向かう電車の中で過呼吸を起こしたりするようになりました。心配した同棲している彼氏とともに受診されました。
来院後
うつ状態が強かったので、休職としました。抗うつ薬を投与し、徐々に気分がよくなり、3か月後には、外出もでき、活気も戻ってきました。しかし、復職のことを考えると、どうしても不安になってしまいます。小さな保育園なので、園長や主任は当分変わらないようです。また、同僚からの情報だと、職場のギスギスした感じはまだ続いているとのことでした。結局、彼氏と旅行したり、友人とコンサートに行ったりは楽しくできるのに、仕事のことを考えると辛いという状態が続き、半年後には、医師と話し合った結果、退職することになりました。その後、もっと大手の保育園に転職し、そこでは元気に働けています。
コメント:
小さな職場ではどうしても人間関係の問題が起きがちです。大企業と違い、すぐに異動できるわけではありません。そんな小さい職場でパワハラ気質の上司がいた場合、なかなか逃げ道がありません。医師としても、できることが限られており、退職やむなし、と助言する場合もあります。
6.大学の勉強についていけず、うつ病になった女性
来院時
大学の看護学科の3年生の20代の女性です。1年生の時から座学についていくのに大変さを感じていました。3年になり、6月から看護の病院実習が始まりました。指導教員から仮題が出され、それをレポートにまとめて、期日以内に提出しないといけないのですが、中々終わりません。そのうち、深夜まで課題に時間をかけるようになり、寝不足で次の日の実習に行くということが続くようになりました。8月ごろから徐々に昼間に体のだるさを感じるようになりました。気分が落ち込むようになり、ますます課題に集中できなくなり、課題の提出も遅れるようになりました。9月になり、指導教員に呼び出され、注意をされた際に、涙が止まらなくなり、心配した教員より精神科の受診を促され、受診しました。
来院後
実習に対して、キャパオーバーは明らかな状態でした。うつ状態である旨の診断書を作成し、大学に提出しました。本人と話し合い、休学せず、課題を少し減らしてもらったり、締め切りを少し待ってもらうなどの配慮をもらい、なんとか実習を乗り切れました。薬は不安止めの頓服のみとしました。その後、無事、4年生になれたとのことでした。
コメント:
看護学生のうつ病は毎年一定数来院されます。ほとんどの方が、実習のきつさについていけなくなったと話します。私も医学生時代に、病院実習を行い、看護学生の実習と現場が被るときがありました。確かに、医学生より看護学生の方が実習がキツイというのは体感としてうなずけるところがあります。医学科より看護学科のほうが、実習における指導教員との上下関係が厳しいのです(私が医学生だった当時は医学部医学科は、授業や実習を多少さぼってもあまり怒られない時代でした)。当院に来て、休学の末に、大学の看護学科や看護学校をやめた方もいらっしゃいます。その後、介護士になったり、一般の事務職になられた方もいました。
7.実はうつ病ではなく躁うつ病だった女性
来院時
30代前半の女性です。高校2年生の時に、急に気持ちが落ち込み、不登校気味になりました。その時、学校の友人関係で悩んでいたようです。いじめられていたわけではなかったようです。その後、大学生の時にも、急に落ち込み、大学に1か月ほど行けなくなり、家に引きこもっていた時期がありました。その時、精神科に受診し、「うつ病」と診断されましたが、数回で受診を中断しました。その後も、年に2~3回は、理由なく落ち込むことが続いていました。今回、落ち込みが強くなり、仕事も休みがちになったので、受診されました。
来院後
診察すると、実は、これまでに「1週間ぐらい異常にテンションが高くなり、おしゃべりになったり、友人を飲み会に誘ったり、服を買いすぎたり」した時期が過去に何度かあったことが判明しました。うつ病ではなく、躁うつ病と診断し、気分安定薬を処方すると、徐々に落ち込むことが少なくなってきました。
コメント:
これはうつ病ではなく、躁うつ病だったケースです。前医でうつ病と診断され、よく聞くと、躁うつ病というケースは時々あります。医療業界には「後医は名医」という言葉があります。後に診察する医師のほうが、以前の治療状況などの情報も加わるので、診断も治療も適切になりやすいのです。私がうつ病と診断し、抗うつ剤で治療してもよくならず、後から違う医療機関に転院し、躁うつ病と診断されたケースもあります。また、私がうつ病と診断し、途中で、躁状態を呈し、やっと躁うつ病と診断しなおし、薬を変えて病状が安定したケースもあります。ここで言いたいのは、私の診断能力がスゴいということでは全くなく、精神科医が詳細に問診しても「躁うつ病というのは、そもそも診断が困難なことが多い」ということです。
8.実はうつ病にアルコール依存症が隠れていた男性
来院時
50代男性です。5年ほど前から気持ちの落ち込みが続いています。特に、職場の人間関係や労働条件が悪いわけではありません。朝からだるさが強く、ここ2か月ほど、仕事を休む日が増えてきました。今回、落ち込みが強くなり、妻と当院を受診しました。
来院後
問診していくと、実は酒量が多いことが判明しました。毎日、ビールの500mlを5本飲んでいるようです。ここ20年ほど、この酒量だったようです。さらに、去年は膵炎を起こし、2週間ほど入院していたことも判明。その際に、消化器科の医師から「今後、絶対に酒を飲まないように」と強く言われていたことも分かりました。しかし、その後も酒はやめていません。当院の医師から、しばらくの間、断酒するように勧めましたが、結局、酒がやめられず、気分の落ち込みも続いたので、アルコール依存症を疑い、アルコールの専門治療をしている精神科に紹介状を書き、行ってもらいました。ただ、結局、その後、断酒が続いたのかは分からずじまいでした。
コメント:
酒を飲んでいると、気分の落ち込みは治りません。特にこのケースのように、すでに体を壊すほど、飲酒している場合は、まずは断酒の徹底が優先となります。もちろん、抗うつ薬を投与することもありますが、酒を飲みながらだと効果もあまり期待できません。難しいことにちゃんと医師側から聞かないと、患者様本人は「ビール1日2~3リットルなんて全然普通の量だ」と思い込んでいる人も多く、自分からは申告しないのです。
9.夫の退職ののち、うつになった女性
来院時
60代前半の女性です。去年、夫が定年退職を迎え、家にずっといるようになりました。今までは専業主婦で、独りで気楽だったのに、夫の昼ご飯も作らなければならず、それが負担に感じるようになりました。もともと夫は本人に対して、モラハラ発言も多く、ずっと我慢してきました。本当は離婚したいのですが、経済的にそれも困難です。娘が2人いますが、2人ともすでに結婚して、親元を離れています。3か月前より、気分が落ち込み始め、食欲も落ち、当院を受診しました。
来院後
落ち込みに対して、抗うつ薬を開始しました。また、医師より、「自分だけの時間を持つように。友達とお茶をするのもいいし、習い事を始めてもいい」と勧めました。習い事を初めて、しばらくしてから、落ち込みは改善してきました。
コメント:
この症例の場合、夫と距離を取ったのが良かったのか、抗うつ薬が奏功したのか、はっきりとはわかりません。ただ、女性の場合、「引っ越し」「子供が学校でいじめにあう」「子供が自立し、独り暮らしを始める」「夫が退職する」「夫に先立たれる」など、人生および家族の節目節目でうつになることが多い傾向があります。もちろん、なんの心理的ストレスがなく、うつ病を発症する人もいますので、今回の症例が、すべて夫のせいだと決めつけるわけにはいきません。
10.もともと不安が強い若年男性
来院時
20代後半の男性です。小さい頃から人見知りで、小学生のころから友人が少なく、いじめられていました。中学生になり、いじめは続き、2年生の4月から卒業までほとんど学校に行かなくなりました。高校に入学しましたが、1年の2学期で、不登校になり、そのまま退学。その後、ずっと家に引きこもっています。これまでにバイトを含め、働いた経験は一切ありません。数か月前から、母に「死にたい」と口にするようになり、心配した母親と一緒に受診しました。
来院後
診察室でも極端におとなしい態度でした。気分の落ち込みと不安を認めました。外出すると、人の目が気になり、緊張して腹痛がしてくるとのことでした。家ではずっとYouTubeを見ており、ほとんど出かけません。話し相手は家族だけです。なんとなく憂鬱な感じがここ1年ほど続いているとのことです。医師より、就労移行支援を勧めましたが、1回見学に入ったのですが、「やっぱり緊張する」と話し、引きこもりを続けています。
コメント:
うつなのか元々の不安になりやすい性格なのかはっきりしない症例です。不安障害(社交不安障害?全般性不安障害?)と診断してもいいのかもしれません。抗うつ薬が不安全体にも効きますので、処方する場合もあります。中には不安が多少和らぐ方もいますが、だからといって社会につながるかはその人次第なところはあり、難しい問題です。ただ、一口に「ひきこもり」と言っても、ベースに知的障害、発達障害、強迫性障害、統合失調症、など色々な精神疾患が隠れていることがあります。